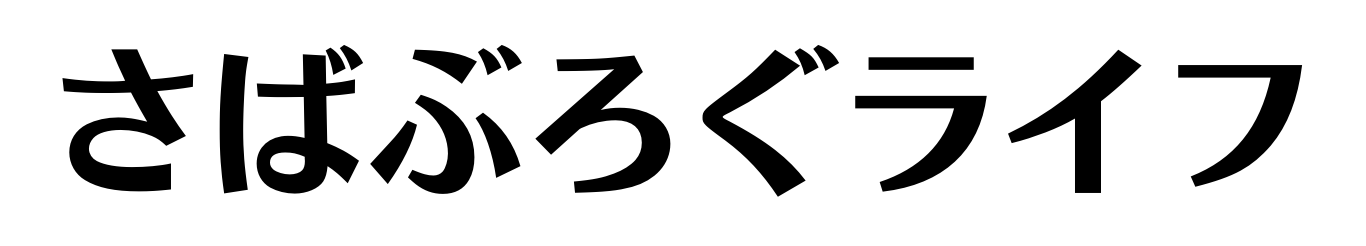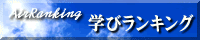「え、なんで?こんなに頑張ってるのに、給料は上がらないし、副業すらダメなの?」
そう思わずにはいられない毎日を送っていませんか?
現代の日本では、物価が上がり続ける一方で、賃金はほとんど横ばい。
総務省の2023年データによると、一般労働者の平均年収は約496万円(※)ですが、これでは生活に余裕を持つのは難しいという声が増えています。
※出典:https://www.stat.go.jp/data/roudou/
さらに困ったことに、副業が許されていない職場もまだまだ多いのが現状。
政府が「副業・兼業の促進」を掲げているのに、あなたの会社はまるで時代に取り残されたように「副業禁止」を掲げ続けていませんか?
「せめて自由に働かせてくれれば…」「生活費を補うためにちょっと稼ぎたいだけなのに」
——そんな思いを胸に、Google検索に「給料安いくせに副業禁止」と入力したあなた。大丈夫です。
この記事では、そんな理不尽な現状を一緒に読み解き、どう向き合っていくかを専門家として丁寧にご案内します。
現役で企業コンサルや副業支援にも携わる筆者が、労働法や経済動向、実際に副業で稼ぐ人の成功例などを交えながら、今すぐできる実践的な対処法をお届けします。
「給料は安い。でも副業もダメなんて、やってられない」
そんなあなたが、一歩踏み出せるヒントをきっと見つけられるはずです。
なぜ「給料安いのに副業禁止」なのか?制度の矛盾を探る

企業はなぜ副業を禁止したがるのか
「副業禁止?今どきそんなこと言ってるの?」と思われがちですが、実は多くの企業が今でも副業を禁止しています。その理由、気になりますよね。
まず企業側が掲げる大義名分としては、「情報漏洩のリスク」と「社員の健康管理」。たしかに、企業秘密を外部に漏らされたり、過労で本業に支障が出るのは避けたいところ。しかし、これはあくまで“表向き”の理由にすぎません。
本音はどこにあるかというと、「社員の忠誠心の確保」と「低コスト労働力の維持」です。副業が許されてしまえば、社員の意識は会社以外にも向いてしまう。
そして、時間の使い方にも幅が生まれます。
すると、会社としては「管理しにくい」「言うことを聞かなくなる」と感じるわけですね。
また、副業が当たり前になると「じゃあ給料低くても仕方ないよね」という“言い訳”が通用しなくなります。
だからこそ、会社は副業をあえて抑え込もうとするのです。
しかし、これは時代の流れに完全に逆行しています。
働き方改革やリスキリング、副業解禁の波が押し寄せる今、私たちが問うべきは「なぜ副業が禁止なのか?」ではなく、「副業禁止がまだ通用してることが異常では?」という視点かもしれません。
法律的には副業禁止はOK?NG?
「副業禁止って、そもそも法律的にアリなの?」この疑問、非常に多くの方が持っています。
結論から言うと——**法律では原則、副業は禁止されていません。**しかし、企業が就業規則で制限をかけることは“ある程度”認められています。
労働基準法では、副業に関して明確な禁止規定は設けられていません(出典:厚生労働省)
一方で、企業が就業規則で副業禁止条項を設けることは可能で、それが「合理的な理由に基づいていれば有効」とされています。たとえば「機密情報の漏洩」「競業避止」「過重労働による本業への支障」などがその理由として認められます。
しかしここで重要なのが、**政府の方針は「副業・兼業の推進」**であるという点です。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2023年改定)において、「原則容認」を明記しました(出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html)
つまり法的には「禁止ではないが、会社次第」。
しかし時代は確実に「解禁」に向かっています。副業を理由に処分する企業は、今後ますます社会的な批判を浴びるでしょう。
収入アップを阻む副業禁止、どう対処すべき?

副業禁止の会社でもできる合法的な稼ぎ方
「うちの会社、副業禁止だから何もできない…」そう感じている方、多いですよね。
ですがご安心を。実は、副業禁止の就業規則がある会社でも合法的に稼ぐ道はあるんです。
まずポイントは、「バレないこと」ではなく、「法律に違反せず、就業規則の範囲内でできる方法」を選ぶこと。たとえば、YouTubeやブログ、noteでの情報発信は、自宅で空いた時間に行える代表的な手段。顔出しや実名を避け、ペンネームで運用すればリスクも軽減されます。
また、「ポイントサイト」「クラウドワークス」「ココナラ」など、スキマ時間で収入につながる副収入源も人気。これらは労働の対価というより、“成果報酬”型なので、勤務先に申告義務が生じないケースもあります(ただし、税務上の申告は必要)。
さらに、書籍出版やイラスト販売、電子教材の販売なども「作品収入」として分類されるため、副業の定義から外れるケースがあります。
ここで大事なのは、**確定申告時に「住民税の特別徴収を回避する」**こと。会社にバレたくない場合、「普通徴収(自分で納付)」を選ぶことで、副業収入が会社に知られにくくなります。
稼ぎ方は一つじゃありません。会社のルールに縛られず、自分で「合法的な選択肢」を見つけましょう。
転職という選択肢も現実的
「もう副業禁止なんて古いよ…」と感じているあなたにとって、転職は実はとても現実的な選択肢です。最近では「副業OK」「リモートOK」「フレックスタイム」など、柔軟な働き方を認める企業が急増中。転職によって、“収入も自由度も”同時に手に入れるチャンスが広がっているんです。
特に注目すべきは、ベンチャー企業やスタートアップ、中小IT企業。これらの企業では「副業推奨」を掲げているところも多く、スキルアップと収入アップの両立が可能です。
また、厚生労働省の調査によれば、「副業制度あり」とする企業は大企業で38.1%、中小企業で16.3%にとどまる(※2022年「副業・兼業実態調査」より)ため、企業選びの段階から「副業可」を明示している企業を優先するのが賢明です。
転職活動を始めるなら、「副業OK求人」に特化した転職サイトやエージェントを活用しましょう。
特に「Green」「Wantedly」「ReWorker」などは副業やリモートワークに理解のある企業が多く、条件検索でもフィルターがかけられるため効率的です。
今の会社に居続けるリスクと、転職で得られるメリット。天秤にかけてみる価値は、十分にあると思いませんか?
そもそも給料が安すぎる日本、その背景と未来
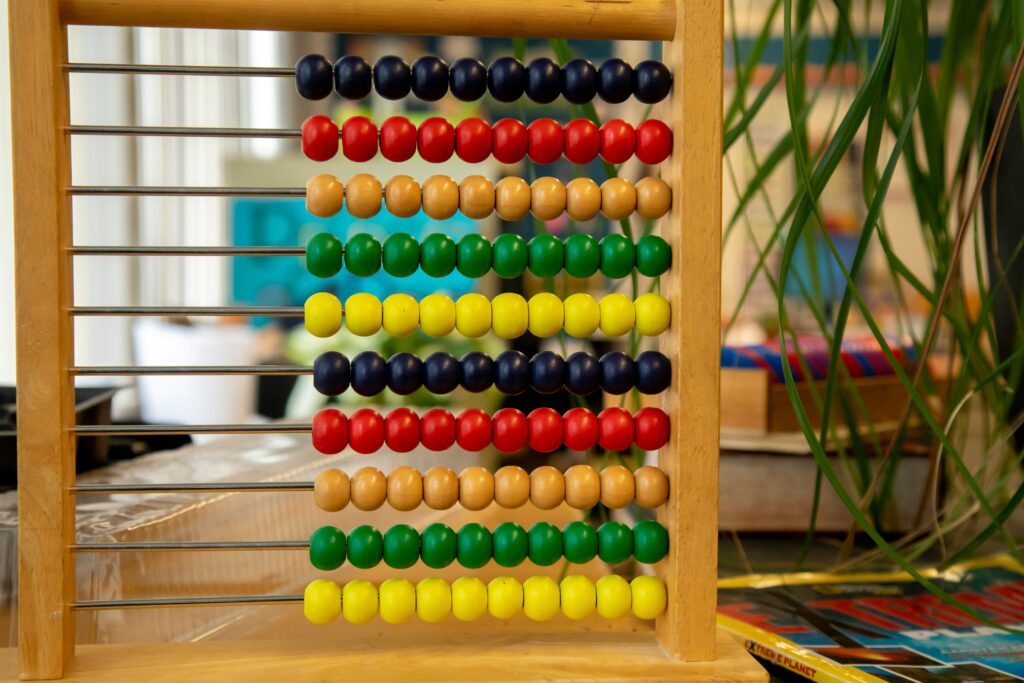
日本の平均給与はなぜ低いのか?
「どうして日本の給料は、こんなに上がらないの?」
多くの人が感じているこの疑問、実はデータで見ても明確な答えがあります。
OECD(経済協力開発機構)の2023年の調査によれば、日本の平均年収は約4万ドル程度で、アメリカやドイツ、イギリスと比べても明らかに低水準です(※出典:https://stats.oecd.org/)。さらに、ここ20年ほど実質賃金はほぼ横ばい。日本だけが取り残されたかのような状況が続いています。
なぜこうなったのか?
要因の一つは、「年功序列と終身雇用」という古い制度。若い時には低賃金でも、年齢を重ねるにつれて給料が上がる設計だったため、企業は初任給を極端に抑えてきました。しかし、少子高齢化・経済低成長の影響で、このモデルが完全に破綻しているのです。
また、多くの企業では正社員の雇用を守るために、非正規労働者に依存する構造が加速。結果、平均値そのものが下がってしまっています。
そしてもう一つの見逃せない点は、「賃上げの交渉文化が根付いていない」こと。欧米諸国のように“自分のスキルに見合った給料を求める”文化が希薄なため、企業も積極的に賃上げしようとしないのです。
この構造が、私たちの「給料安い」の根本にあります。
このままだとどうなる?生活と将来設計への影響
給料が上がらないまま、物価だけが上がり続ける——この状況が続いたら、私たちの生活はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、**「生活はどんどん苦しくなり、老後の備えもできなくなる」**のが現実です。
実際、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する調査(2023年)」によると、単身世帯の約40.5%が貯金ゼロという衝撃的なデータが出ています。
出典:https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/
この数字が示しているのは、働いているのに生活に余裕が持てない人が急増しているということ。そして将来的には、老後資金どころか、緊急時の備えすらままならないまま高齢期を迎えるリスクがあるということです。
さらに、日本年金機構が示すモデルケースでも、年金受給額だけでは生活費が月5万円〜10万円ほど足りないとされています。この「老後2000万円問題」が現実味を帯びてくるのも当然です。
このまま現状維持を選び続けると、あなたの生活は「節約と不安」の連続になります。
だからこそ、今こそ「副業」や「転職」「投資」など、“収入の選択肢”を広げることが、将来への不安を少しでも和らげるカギになるのです。
まとめ:あなたの働き方、今こそ見直し時かも

副業禁止の壁を乗り越えるヒント
「給料は安い、でも副業もダメ」——そんな現実に悩む人は、決して少数派ではありません。
でも安心してください。この壁、乗り越える方法は確実にあります。
まずは、会社のルールを正しく理解すること。副業禁止の背景や就業規則を確認し、「何がダメなのか」「どこまで許されるのか」を把握することが第一歩です。その上で、ガイドラインに沿った合法的な稼ぎ方を選びましょう。
また、転職やスキルアップ、副業型マイクロビジネスなど、“一つの会社に縛られない働き方”も今では珍しくありません。
リスクを最小限に抑えながら、柔軟に収入源を持つこと。それがこれからの時代の「当たり前」になっていくでしょう。
重要なのは、“誰かに決められた人生”ではなく、“自分で選び取る人生”を目指すこと。
あなたには、今の場所だけに縛られない自由があります。
自分の未来を守る選択をしよう
最後にお伝えしたいのは、「何もしないことが、いちばんのリスクになる時代」だということです。
副業を始めるか、転職するか、今の会社でスキルを高めていくか——その選択肢はあなたの手の中にあります。
「給料安いくせに副業禁止」にただ不満を抱いているだけでは、何も変わりません。
変えるのは、あなた自身の“行動”です。
もちろん、すぐに大きく動くのは難しいかもしれません。でも、調べる・学ぶ・準備する——それだけでも確実に未来は動き始めます。
経済的不安や将来の生活にモヤモヤしている今だからこそ、一度立ち止まって「自分はこのままでいいのか?」を問い直してみましょう。
あなたの人生は、あなたのものです。
小さな一歩が、やがて大きな安心につながります。