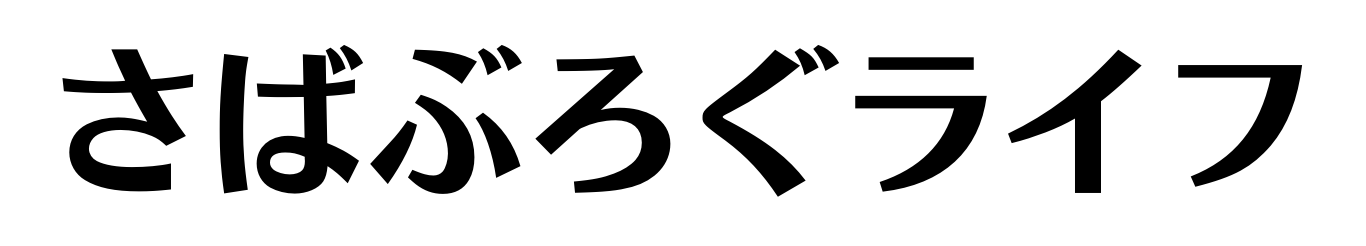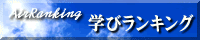マウントを取りたがる人ってどんな人?
職場や友人関係、SNSなどで、「なんでこの人、いつも上から目線なんだろう…」と感じたことはありませんか?明言はしなくても、何かと自分のほうが上だとアピールしてくる人——それがいわゆる「マウントを取りたがる人」です。接しているとモヤモヤしたり、自己肯定感が下がったりして、知らず知らずに心が疲れてしまいますよね。
この記事では、マウントを取りたがる人の明確な特徴から、その裏にある心理、そして上手に対処する方法までをわかりやすく解説します。自分が悪いわけではないことを理解し、少しでも人間関係がラクになるきっかけになれば幸いです。
この記事でわかること
- マウントを取りたがる人の心理とその背景
- 典型的な10の特徴と具体的な言動例
- マウントを取られやすい人の共通点
- 無理せずできる対処法と考え方のコツ
マウントを取りたがる人とは?その心理背景を探る
「マウントを取る」とは、他人よりも自分が上だとアピールし、優位性を誇示しようとする行動のことです。職場・友人関係・SNSなど、あらゆる場面で遭遇することがあり、「なんだかモヤモヤする」と感じている人も多いのではないでしょうか。このセクションでは、そもそもマウント行動とは何か、なぜ人はそうした態度を取るのか、そしてその裏にある心理をひも解いていきます。
「マウント」とはどういう行動なのか
マウントとは、会話や行動の中で、相手よりも自分が上だと示す言動を指します。たとえば以下のような行動が該当します。
| シチュエーション | 例 |
|---|---|
| 職場 | 「私なんてもっと忙しいのに頑張ってるよ」 |
| 友人関係 | 「そんなの昔から知ってたよ」 |
| SNS | 「高級レストラン行ってきた~」と頻繁に投稿 |
こうした発言の特徴は、表面的にはアドバイスや雑談のように見えて、実は相手を下に見て安心したいという心理が潜んでいる点です。
なぜ人はマウントを取りたがるのか
マウントを取る人の多くは、他人よりも優れていたいという承認欲求を強く持っています。
人間関係における比較は自然なものですが、それが過剰になると、他者を見下すことでしか自分の価値を保てない状態になります。これは「劣等感の裏返し」であり、本人も無自覚な場合が多いのです。
心理学では、これを「防衛機制」と呼ぶこともあります。自分の弱さや不安を隠すために、優位な立場を演じるという行動に出てしまうのです。
マウントを取る人が抱える“内なる不安”とは
実は、マウントを頻繁に取る人ほど、心の奥で強い不安や孤独感を抱えているケースが多いです。
- 自分に自信がない
- 他人と比較しないと安心できない
- 誰かに認めてもらいたいという欲求が強い
これらは、過去の育ち方や人間関係の影響で形成されていることもあります。たとえば、常に親から「もっと頑張れ」と言われ続けた人は、成果でしか愛されないと感じやすく、マウント行動でそれを補おうとすることがあります。
マウントを取りたがる人とは?その心理背景を探る
「マウントを取る」とは、他人よりも自分が上だとアピールし、優位性を誇示しようとする行動のことです。職場・友人関係・SNSなど、あらゆる場面で遭遇することがあり、「なんだかモヤモヤする」と感じている人も多いのではないでしょうか。このセクションでは、そもそもマウント行動とは何か、なぜ人はそうした態度を取るのか、そしてその裏にある心理をひも解いていきます。
「マウント」とはどういう行動なのか
マウントとは、会話や行動の中で、相手よりも自分が上だと示す言動を指します。たとえば以下のような行動が該当します。
| シチュエーション | 例 |
|---|---|
| 職場 | 「私なんてもっと忙しいのに頑張ってるよ」 |
| 友人関係 | 「そんなの昔から知ってたよ」 |
| SNS | 「高級レストラン行ってきた~」と頻繁に投稿 |
こうした発言の特徴は、表面的にはアドバイスや雑談のように見えて、実は相手を下に見て安心したいという心理が潜んでいる点です。
なぜ人はマウントを取りたがるのか
マウントを取る人の多くは、他人よりも優れていたいという承認欲求を強く持っています。
人間関係における比較は自然なものですが、それが過剰になると、他者を見下すことでしか自分の価値を保てない状態になります。これは「劣等感の裏返し」であり、本人も無自覚な場合が多いのです。
心理学では、これを「防衛機制」と呼ぶこともあります。自分の弱さや不安を隠すために、優位な立場を演じるという行動に出てしまうのです。
マウントを取る人が抱える“内なる不安”とは
実は、マウントを頻繁に取る人ほど、心の奥で強い不安や孤独感を抱えているケースが多いです。
- 自分に自信がない
- 他人と比較しないと安心できない
- 誰かに認めてもらいたいという欲求が強い
これらは、過去の育ち方や人間関係の影響で形成されていることもあります。たとえば、常に親から「もっと頑張れ」と言われ続けた人は、成果でしか愛されないと感じやすく、マウント行動でそれを補おうとすることがあります。
マウントを取りたがる人の特徴10選
「なんかこの人、いつも自分を上に見せたがるな…」そんな違和感を覚えた経験はありませんか?マウントを取りたがる人には、ある共通した言動パターンがあります。このセクションでは、よく見られる特徴を10個に絞って具体的に解説します。該当する人を見つけやすくなるだけでなく、自分自身にもその傾向がないか、客観的に見直すヒントにもなります。
常に自分語りをしてくる
マウント気質の人は、会話の主導権を握りたがる傾向があります。たとえば、誰かが話している最中に「私のときはもっと〜だった」と割り込んで自分の話にすり替えることが多いです。
これは、話題の中心になって優越感を得たいという心理から来ています。自分が話題の中心でないと不安になってしまうため、無意識にでも「自分の経験の方がすごい」とアピールしてしまうのです。
また、相手に質問せず、自分の話ばかりする人も要注意です。会話のキャッチボールが成立しないのは、マウント取りタイプの典型例といえます。
相手の話を遮って自分の話にすり替える
「それってさ、私も前に経験したんだけど…」というように、相手の話を遮り、自分の話題へすり替える行動もマウントの一種です。
このタイプの人は、相手の話をじっくり聞くことが苦手です。それよりも、「自分の方がもっとすごい」「私の経験の方が価値がある」とアピールしたくてうずうずしています。
実際には会話の流れを無視してでも、自分の武勇伝や成功体験を差し込んでくるため、聞かされる側は疲れてしまうのが特徴です。
SNSで「幸せアピール」が多い
現代では、SNSでもマウントが顕著に現れます。
- 高級レストランでの食事写真
- ブランド品の自慢
- 仕事の成功報告
これらが頻繁すぎる場合、「私ってこんなに充実してるのよ」と周囲に優越感を示したい欲求がにじみ出ています。
もちろん、SNSでポジティブな投稿をするのは自由ですが、他人の現実と比べて落ち込ませるような投稿が多い場合は、注意が必要です。裏を返せば、リアルな人間関係において満たされておらず、「SNS上でだけでも自分を誇示したい」という心理状態ともいえます。
常に競争意識を持っている
マウントを取りたがる人は、何事も「勝ち負け」で判断する癖があります。
たとえば:
- 年収や役職を比較してくる
- 子どもの進学先で張り合ってくる
- 恋人や配偶者のスペックを自慢してくる
このように、あらゆることに“順位”をつけたがる傾向があり、相手より少しでも上に立とうとします。実はこの心理の裏には、「劣等感」や「自信のなさ」が隠れている場合が多いのです。
6.アドバイスの形で見下してくる
「あなたのためを思って言ってるんだけど…」という言い回しに心当たりはありませんか?
これは、マウントを取る人がよく使う**“善意に見せかけた見下し”のテクニック**です。
- 「もっと努力すればあなたもできるよ」
- 「私はこうやって成功したから、真似してみたら?」
一見すると親切なアドバイスに見えますが、実際には「自分の方が上」「あなたはまだまだ未熟」というニュアンスが含まれています。
本当に相手を思う人は、相手の状況や気持ちを尊重した言葉を選びます。その違いに注意しましょう。
上から目線の話し方が多い
マウントを取る人は、無意識のうちに**「自分が正しい」「あなたは間違っている」**という立場で話す傾向があります。話し方のトーンや言葉選びにも、それが表れることが多いです。
たとえば以下のような言い回しが典型です。
- 「そんなの常識だよね?」
- 「え、まだそれやってないの?」
- 「私ならもっと早くやるけどな」
こうした言葉には、「あなたはレベルが低い」という含みがあります。直接的な悪口ではなくても、相手に劣等感を与えるような発言を繰り返すのは、まさにマウント行動の一種です。
7.他人の成功を素直に喜べない
誰かが良い報告をしたとき、マウントを取る人は**「すごいね!」と素直に称賛することができません**。
代わりに、こんな反応をすることがよくあります。
- 「でもそれって運がよかっただけだよね?」
- 「私も前に似たようなことあったけど、その後大変だったよ」
- 「まぁ私の知り合いはもっとすごいけどね」
これは、相手が「自分より上」に行くことへの嫉妬や危機感から出てくる言動です。自分のポジションが脅かされると感じると、相手の成果を引き下げようとするのが特徴です。
8.自分の話題になるとテンションが上がる
会話中、自分の話になると急に饒舌になったり、テンションが明らかに上がる人もマウント気質の可能性があります。
- 「私の時はさ〜」「それより私なんて…」
- やたらと身振り手振りが増える
- 声のトーンが高くなり、早口になる
これは、「注目されている=優位に立っている」と感じて快感を得ているサインです。逆に、他人の話には興味を示さず、反応が薄くなる傾向があります。
9.他人の欠点をすぐに見つけて指摘する
マウントを取りたがる人は、他人の弱点やミスに非常に敏感です。わざわざ指摘することで、「自分の方が正しい・優れている」と示そうとします。
- 「それ間違ってると思うよ」
- 「なんでそんなことも知らないの?」
- 「前も同じこと言ってたよね?」
こうした言動は、一見すると注意やアドバイスに見えるかもしれません。しかし実際には、「相手を下に見たい」という優越感を満たすための行動になっている場合が多いです。
10.マウントを取っている自覚がない
一番やっかいなのが、「本人がマウントを取っていることに気づいていない」パターンです。
- 本人は「普通に話しているだけ」と思っている
- 「自分は正直なだけ」と自己正当化している
- 指摘すると逆ギレされることも
このタイプの人は、他人の感情への共感力が低いことが多く、自分の言動が相手にどう影響するかを考える習慣がありません。結果として、人間関係のトラブルを頻繁に引き起こします。
マウントを取られやすい人の特徴とは?
マウントを取ってくる人の言動に悩まされる人は多いですが、実は「取られやすい側」にも一定の傾向があります。このセクションでは、マウントを取られやすい人の特徴を掘り下げることで、今後の人間関係のストレスを減らすヒントを提供します。自分を責める必要はありませんが、少し視点を変えることで関係性がラクになることもあります。
謙虚すぎて自己主張が少ない人
一見すると「いい人」「気が利く人」と思われがちなこのタイプ。しかし、マウント気質の人からすると**“反論されない都合のいい相手”**と見なされやすい傾向があります。
- 「そうですね」と何でも受け入れてしまう
- 自分の意見を後回しにしてしまう
- 会話の中で自分の話をしない
こういった姿勢は、相手に主導権を渡しすぎてしまうため、結果として相手が優位に立つ隙を与えてしまうのです。謙虚さは美徳ですが、「言いなり」にならないことも大切です。
自信のなさが言動ににじみ出ている
マウントを取りたがる人は、「弱っている人」や「自信がなさそうな人」に自然とマウントを取りたがる傾向があります。
- 言葉遣いがいつも曖昧
- 目を合わせられない
- いつも周囲の反応を気にしている
このような態度は、相手に「私はあなたより下です」と暗に伝えてしまうことになりかねません。
ポイントは、自分の価値を自分で下げないこと。完璧でなくてもいいので、「私はこれでいい」と自分を肯定する意識を持つことが、マウント回避の第一歩になります。
「いい人」でいようとしすぎる人
- 相手を怒らせたくない
- 嫌われたくない
- 和を乱したくない
こうした思考が強い人ほど、マウント気質の人につけ込まれやすくなります。なぜなら、「反論されない」「言い返されない」ことが分かっているからです。
実際、マウントを取りたがる人はターゲットを選んでいます。気が強い人や自分を持っている人にはあまり強く出られませんが、優しすぎる人には強気に出る傾向があります。
「いい人」でいようとするあまり、自分を犠牲にしてしまう人は特に注意が必要です。適度な「ノー」の姿勢が、健全な関係を築く鍵になります。
上手な対処法と心がラクになる考え方
マウントを取ってくる人に対して、毎回イライラしたり傷ついたりしていては、こちらの心が持ちません。かといって、真っ向から対抗しても消耗してしまうだけです。このセクションでは、マウントに対して無駄にエネルギーを使わず、心を守りながらスマートに距離を取る対処法をご紹介します。
受け流す技術:「すごいですね」で終わらせる
マウントを取る人は、「すごい」「さすが」「知らなかった」と言われることで満足します。つまり、本気で勝負しようとしなければ、実は簡単に会話を終わらせることができるのです。
おすすめのリアクション:
- 「へぇ〜すごいですね」
- 「さすがですね」
- 「そうなんですね〜(感情をこめずに)」
これらは一見相手を持ち上げているようで、**それ以上会話を発展させない“会話の終着点”**でもあります。あえて深堀りせず、相手に「勝った気分」だけを与えてスルーするのが、精神的にも効果的な戦略です。
境界線を引く:「無理に付き合わない」選択
マウントを取ってくる人と、いつも付き合わなければいけない理由はありません。
- ランチを毎回一緒にしない
- SNSのフォローを外す、ミュートする
- 必要最低限の連絡だけにする
こういった距離の取り方は、「悪いこと」でも「冷たいこと」でもありません。自分のメンタルを守るための“境界線”を引く行為です。
境界線を引けない人ほど、ストレスを溜め込みやすくなります。相手を変えるのは難しくても、自分の行動と環境は変えることができるのです。
自分もマウント返しをしないように意識する
注意すべきは、マウントを取られて悔しいあまりに、**自分もつい「やり返したくなる」**という心理です。
- 「でも私は○○できたけどな」
- 「逆に私はあのとき○○だったよ」
こうした返しは、結果的にマウントの応酬を生み、関係性を悪化させるだけです。悪気がなくても、「自分を正当化したい」という気持ちが強くなると、知らないうちに自分も同じ行動を取ってしまうことがあります。
大切なのは、「張り合わない」「同じ土俵に立たない」意識です。勝ち負けではなく、“自分が心地よくいられる距離感”を大切にすることで、自然と心も軽くなっていきます。
まとめ
マウントを取りたがる人との関係に悩んでいる方は少なくありません。しかし、そういった人の言動には「自信のなさ」や「承認欲求」といった心理的背景があることを理解すると、過剰に反応せずにすむようになります。
本記事では、マウントを取る人の特徴を10個にわたって紹介し、その心理や対処法、さらに取られやすい人の傾向まで掘り下げてきました。
ポイントは、「自分が悪い」と思い込まず、相手のパターンを見極めて、上手に受け流すこと。また、無理に付き合おうとせず、自分にとって心地よい距離感を保つことも大切です。
人間関係で疲れないためには、**自分の心を守る“線引き”と“俯瞰の視点”**が欠かせません。相手に振り回されず、ラクに生きるための第一歩として、ぜひ今回の内容を実生活に活かしてみてくださいね。