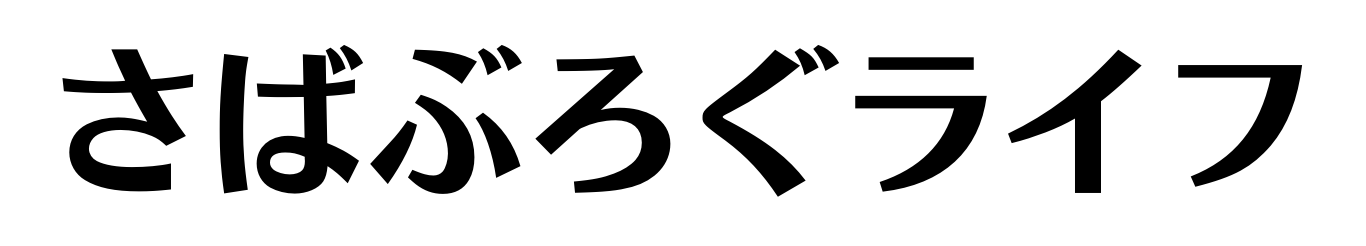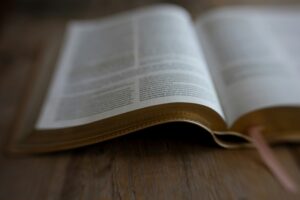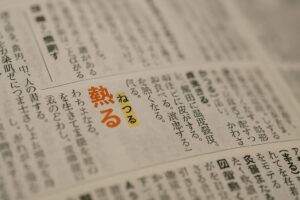ついていく って漢字どう書けばよかったっけ
文章を書いていると「ついていく」と「ついて行く」のどちらを使えばいいのか迷った経験はありませんか? 一見どちらも正しく見えますが、実は辞書や文化庁の基準では推奨される表記が明確に定められています。
誤った漢字変換をすると、ビジネス文書や試験で減点されたり、相手に不自然な印象を与える可能性もあるのです。
この記事では、迷いやすい「ついていく/ついて行く」の正しい使い分けをわかりやすく解説します。
表記の理由を理解することで、文章に自信が持てるようになり、相手に安心感を与える書き方ができるようになります。
この記事でわかること
- 「ついていく」と「ついて行く」の正しい表記ルール
- 「付いて行く」との違いと誤用になりやすい理由
- ビジネス文書や日常でのおすすめ表記
- よくある疑問と漢字の正しい使い分け
ついて行く/ついていくはどちらが正しい?
最初に結論を伝えると、現代の公的な文章や辞書では「ついていく」とひらがな表記するのが最も無難で正しいとされています。「ついて行く」と漢字を使っても意味は通じますが、文化庁や新聞社などの基準では仮名書きを推奨しています。そのため、迷ったときは「ついていく」と書けば安心です。
表記の揺れが生まれる理由
「ついていく」は「行く」という動詞が後ろに付くため、本来は動詞の活用を漢字で書く「行く」と表記することも可能です。しかし、複合動詞になると可読性が下がりやすいため、戦後の国語政策で「仮名書き優先」が推奨されました。これが「ついていく」と「ついて行く」の表記ゆれを生んでいる大きな理由です。
現代仮名遣いと文化庁の見解
文化庁の「現代仮名遣い」では、複合動詞の多くをひらがなで書くように指導しています。特に「行く」は助動詞的に使われることが多いため、読みやすさを優先して「いく」と表すのが一般的です。したがって、公式な文書や学習指導要領でも「ついていく」とされます。
辞書での扱い
主要な国語辞典を確認すると、例えば以下のような記述があります。
- 広辞苑:ついていく【付いて行く/付いて行く】→見出しは「ついていく」が基本
- 明鏡国語辞典:「ついていく」で掲載し、漢字表記は補足扱い
このように、辞書上も「ついていく」が優先形であり、「ついて行く」は補足的に扱われています。
「付いて行く」と「付いていく」の違い
結論から言えば、「付いて行く」と漢字で書くのは基本的に誤用とされ、『ついていく』と書くのが正しいと考えてください。「付く」は「物がくっつく・属性が備わる」という意味であり、「後を追って進む」というニュアンスの「ついていく」には本来使われません。つまり、「付いて行く」は意味的に不自然になりやすいのです。
「付く」と「着く」の意味の違い
日本語の「つく」には複数の漢字が当てられます。
- 付く:物理的にくっつく、属性が添う(例:ほこりが付く、値段が付く)
- 着く:到着する、ある場所に行き着く(例:駅に着く、目的地に着く)
- 就く:職業や役割につく(例:仕事に就く、役職に就く)
「ついていく」は「人の後を追って進む」「流れに合わせて進む」という意味なので、どの漢字もピッタリは当てはまりません。そのため、仮名で書くのが適切です。
「付いて〜」は誤用とされやすいケース
例えば次のような文章は誤用の典型です。
× 友達に付いて行く
× 流行に付いて行けない
これらは「付く(くっつく)」ではなく「従う」「同行する」の意味なので、「ついていく」「ついていけない」と仮名で書くのが自然です。
使われがちな場面の具体例
一方で、日常的に「付いて行く」と書いてしまう人も少なくありません。特にビジネスメールや作文で「漢字を使った方がかっこいい」と思い、誤って変換してしまうパターンです。しかし公的文章や試験で使うと減点対象になる場合もあるため、あえて漢字にせず「ついていく」と書くのが正解です。
ビジネス文書や日常でのおすすめ表記
結論から言えば、ビジネスや公的な場面では必ず「ついていく」とひらがなで書くのが最も安全です。日常的な会話文や小説などでは「ついて行く」としても意味は通じますが、相手に誤解を与えないためには、統一感と読みやすさを重視して仮名書きにするのがベストです。
公的文書で推奨される表記
新聞社の用字用語集や文化庁の「現代仮名遣い」では、複合動詞の多くをひらがな表記に統一する方針がとられています。
例:
- 新聞記事 → 「彼は上司についていった」
- 教育現場 → 教科書や試験問題でも「ついていく」を採用
公的ルールに準じるなら「ついていく」が正解となります。
メール・チャットではどちらを選ぶべきか
ビジネスメールや社内チャットでは、スピード感や読みやすさが重視されます。
- 「ついていく」:誰にでも伝わる安心感がある
- 「ついて行く」:一見丁寧に見えるが、相手によっては誤用と受け取られるリスクがある
そのため、無難に「ついていく」を使う方が社内外での印象が安定します。
読みやすさと統一感を重視するコツ
文章全体の中で「ついていく」と「ついて行く」が混在すると、読者に「どちらが正しいのだろう?」と余計な疑問を与えてしまいます。書き手の立場としては以下のルールで統一すると安心です。
- 公式文章・ビジネス文書:必ず「ついていく」
- 日常会話・小説など自由な文:好みに応じて「ついて行く」も可
- 学習や試験:減点を避けるため「ついていく」に統一
こうしてルールを自分の中で決めておくと、迷わず書けるようになります。
よくある疑問Q&A
ここでは「ついていく」をめぐって特によくある疑問を整理します。結論を先に言うと、基本的にすべて仮名書きにすれば安心です。漢字表記は例外的に意味を区別したい場合のみ使う、と覚えておけば迷いません。
「ついていけない」と「ついていける」の場合は?
- 正:流れについていけない
- 正:授業についていける
これらはどちらも「同行・同調する」という意味なので、やはり「付く」や「着く」とは異なります。したがって漢字を使わず、すべて仮名で統一しましょう。特に試験の作文やビジネスメールでは、この書き方が減点リスクを避ける最良の方法です。
小説や会話文での表記は?
文学作品やセリフでは、あえて「ついて行く」と漢字にする例もあります。これはリズムや雰囲気を重視する表現上の工夫で、厳密な国語ルールというより「作家の裁量」です。読者に違和感を与えない範囲であれば許容されますが、実用文書では避けた方が無難です。
漢字で「付く」「着く」を使うべき場面
「ついていく」では漢字を使わないのが原則ですが、別の場面では正しく使い分ける必要があります。
- 付く:値段が付く、色が付く、名前が付く
- 着く:駅に着く、家に着く、目的地に着く
- 就く:職に就く、任務に就く
このように、それぞれ意味が異なります。「ついていく」はあくまで「同行する・従う」なので、これらの漢字を無理に当てはめると誤用になってしまうのです。
まとめ
「ついていく」と「ついて行く」のどちらが正しいのかという疑問は、多くの人が一度は迷うポイントです。結論としては、公的文書・ビジネス文章・学習の場では必ず「ついていく」とひらがなで書くのが正解です。理由は、文化庁の現代仮名遣いや主要な辞書で「ついていく」が基本形とされているからです。「付いて行く」とすると一見丁寧に見えますが、「付く」の意味とは異なるため誤用になりやすく、読者に違和感を与える恐れがあります。
また、小説や会話文では雰囲気を重視して「ついて行く」と漢字を用いるケースも見られます。ただし、これはあくまで表現上の選択であり、ビジネスや教育の現場では推奨されません。統一感と読みやすさを優先して仮名表記するのが無難です。
迷ったときに役立つ判断基準は次の通りです。
- 公式文章・試験・メール → 「ついていく」一択
- 小説や創作 → 表現意図があれば「ついて行く」も可
- 意味を区別する場合 → 「付く」「着く」「就く」を正しく使う
このように整理しておけば、もう変換のたびに迷うことはありません。安心して文章を書けるように、自分の中でルールを決めておくことをおすすめします。